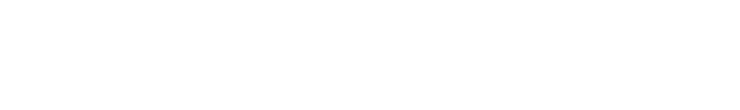個展が終わって一息ついたので、2018年を振り返ってみようと思う。
ことしわたしは、自分の人生で大きな意味を持つ「がん経験者としての自分」と向き合うこととなった。
これまでほとんど人に話すこともなかったのに、なぜ今になってブログやSNSで公表したのかといえば、あの時はそうしたいと思ったからとしか言いようがない。
これを書いている12/27は、ちょうど30年前わたしが手術を受けた日にあたる。12/30だと思っていたけど、カルテを確認したら12/27だった。記憶ってあいまいだ。
30年前がどういう日だったかというと、昭和最後の年、天皇陛下が重体の時期だった。崩御されたのが翌年1/7、わたしは病院のベッドの上で小渕さんの持つ「平成」の文字を見た。あれから30年、その平成も終わろうとしている。
わたしが抱いている途方もない喪失感の正体が何なのか、この一年ずっと考えていた。解放されたいと思って公表してみたけど、解放されるどころか精神的にはどんどん追い込まれてしまった。でも最近になって、自分が何に苦しんでいたかがようやくわかった。
それは、思春期の喪失感だった。
13歳ころから17歳まで、わたしは身体のことで随分悩んでいた。誰にも言えずひとりで抱え込み、最悪な形でそれが表面化したのだ。
だから同じ病気になった違う年齢の人よりも、同世代で虐待をうけたり性犯罪被害を受けた人への共感度がたかい。

この仕事をしていると「好きなことが仕事にできていいですね」と羨ましがられることがある。でもわたしもラクして生きてきたわけではないし、まばゆく見えるあのひとも、実は大変な問題を抱えているかもしれない。
自分のパーソナリティを公表するかしないかは個人の自由だ。それにひとが思い思いの反応をするのは仕方ないことなのだろう。
大きな悩みを抱え誰かに話を聞いてほしいと思っているひとには、「話しただけでは楽にならないよ」と言いたい。一瞬楽になった気がしても問題が消えてなくなるわけじゃない。
そしてもし身近にがんの人がいたなら、その人を自分のストーリーに招くのではなく、あなたがその人のストーリーの聞き役となってそっと見守ってあげてほしい。
患者のストーリーは一人称だけど、家族のストーリーは二人称、友人のストーリーは三人称で読み解くべきだ。
がん経験はわたしの個性のひとつであって、決してわたしを形作るものではない。
今こうしていられるのはがんになったからでも治ったからでもなく、自分の努力であると自信を持って言える。
がんという器のなかで生きるのではなく、がんという器をもって生きていく。それに気づくのに30年もかかってしまった。
そして今やっと、自分の人生が好きになれそうな気がしている。

この投稿を書いていたら幡野広志さんの新しいnoteが公開された。肺炎で入院していると書いてある。
正月またぐ入院はせつないものだ。そして正月でも休みなく働く介護や医療従事者には本当に頭が下がる。
休みがないとこぼす我々の職業も、彼ら彼女らにくらべれば気楽なものだ。